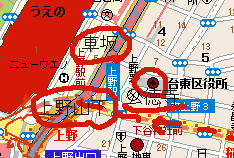|
落語「白浪看板」の舞台を歩く
六代目三遊亭円生の噺、池波正太郎原作「白浪看板」(しらなみかんばん)によると。
昔、夜兎(ようさぎ)角右衛門という大泥棒が居た。
金持ちは世の中から金銭を奪って私腹を肥やしている。だから、それを奪うのは、元に戻す事だから正しい事で、大いに盗んでも良いという。泥棒にも三分の理があるという、屁理屈の上にお盗(つとめ)をしていた。
話は遡って、遠州浜松の宿に泊まって居た時、男の子の捨て子があった。宿帳には江戸日本橋・通り一丁目木綿問屋亀屋義八の名で泊まっていた人品の良い旦那が、子が無いのでその男の子をもらい受けた。京大阪にも家を持っている、角五郎であった。本拠は江戸・根津門前で料理茶屋「すすきや」をやっていて、おようと言う女房がいた。大泥棒角五郎は子供の名を角右衛門と名付けみっちりとお盗(おつとめ、強盗)を教えた。そして立派(?)に成人した。
息子角右衛門は19歳の時、明和4年12月四谷御門前のロウソク問屋「伊勢屋黒兵衛」方に十数名で忍び込み、総指揮を執り982両の金を強奪した。これが初お盗(つとめ)で、仲間内でも大いに株を上げた。
25歳の時、父親角五郎が病の床で、二代目以下に夜兎の三箇条の金看板を読み上げ、それに反した盗みはしてはいけないと遺言して逝った。
一、盗まれて、後々その家が困るような金は盗んではならい。
一、人を殺傷してはならない。
一、女を手込めにしてはならない。
これを、守らない手下が居たら、親分のお前が責任を取らなくてはならない。と強く申し聞かせた。
四十一歳の春、寛政元年2月、浅草鳥越にある松寿院(しょうじゅいん)門前の花屋に参謀格の前砂(まいすな)の捨造を訪ねた。京でのお盗もほとぼりが冷めたので、今度は京橋大根河岸海苔の大問屋「長崎屋」は悪どい金貸しもやっているから、そこにしようと打ち合わせに来た。後、二回ぐらいで隠居でもして、のんびり暮らしたいと、言い合った。
花屋を後に、新堀端を菊屋橋に出、左に曲がり車坂に向かって歩いていた。風が強い中、若い男が50両の金を落としたと探し回っていた。どうしても見つからなかったが、広徳寺脇で右腕のない女乞食が声を掛けた。袱紗に包まれた金を拾ったので、若者に返してあげた。早々に、女乞食は立ち去って居なかったので、車坂で探し出し、上野山下にある有名な高級料理屋「浜田屋」に連れて行った。仲居は嫌な顔をしたが、部屋に上げ、鰻をご馳走した。何で大金を懐に入れず返したか聞くと、「乞食は世間のお余りで生活させて貰っている。その義理で世間に何らかのお返しをするのが、我々です。看板を掛けるように、それは当たり前の事です。その看板を掛けていないとこんな商売出来ません」、角右衛門は人の道、仁義を感じた。女乞食はお幸と言い、五~六十に見えたが、二十五だと言う。9年前駿府の府中、紙問屋「大和屋」に泥棒が入り、賊の一人に右腕を斬られ、その身体ではお勤めは出来ないと暇を出され、身寄りがないからこの様になってしまった。と言う。
根津門前の自宅に戻り、女房とまんじりともせずに相談し、下谷万年町にある乞食の溜まりに出掛けた。お幸を探したが、既に亡くなっていた。昨日の食事、頂いたお金は極楽のようだったという。その思いを抱いて、首を吊っていた。
その足で、浅草鳥越にある前砂の捨造を尋ね、昨夜からの話をした。お盗は我々がやったが、刀を抜いたのはむごい事を平気でする、綱六であった。伊勢の桑名に居る綱六を切りに捨造を遣わせた。
先代からの金看板に泥が付いたと、その場から火付け盗賊改め役、長谷川平蔵に自首した。
白砂で取り調べると、金看板に背かず、仕事をしてきたが、手下に不心得者が居たので、責任を取って自首したと申し述べたが、平蔵はそんなのベニヤ板だと言い放った。女乞食の看板と角右衛門の看板では大違い、その差が解るまで考えて、その真が解った時に打ち首にすると言い渡した。
その後2年牢屋にいたが、長谷川平蔵に引き出され、人の道を蕩々と言い聞かされ、涙を流し悔い改めた。
首を切って欲しいという願いに、平蔵は命をかけるなら国の為に働けと、彼の密偵になって数々の大仕事をこなした。
寛政6年、くちなわの平十郎という大悪党が居た。くちなわとはヘビの事で、ヘビでもマムシのような悪党であった。平蔵が潜伏先を見つけて手下と共に捕縛に向かった。角右衛門と平十郎は腕は互角であったが、角右衛門は残忍な平十郎に気迫に追いつめられて、肩先からザックリと斬られてしまった。二の太刀を振りかぶった時、同心が横から十手で腕を叩き、刀を落とした隙を取り押さえた。
虫の息の中で、これで私の金看板も本物になりました。と悔い改め、安堵の中で成仏した。
平蔵は屋敷内に角右衛門稲荷を祀り、朝夕に礼拝をしたという。
1.池波正太郎原作「白浪看板
」
池波正太郎の代表作の一つ。日本の文庫が2000万部以上売れているシリーズは、司馬遼太郎『竜馬が行く』全8巻と、池波正太郎さん『鬼平犯科帳』全24巻のみ。後者は第1巻だけでも累計で150万部以上刷られている。しかも、池波さんの生前にほぼ50万部、逝ってから100万部、増刷頻度も早くなった。私の友人も全巻をいまだ読み直して、数回目だと言っています。
この話は1965年に発表した短篇「白浪看板」(『別冊小説新潮』夏号)に掲載されたもの。
時代として、江戸が開かれて約100年が経った頃で、文化・経済が爛熟してきて、生活の貧富の差が大きくなって、庶民の不満も鬱積してきた頃です。大泥棒は大金持ちしかおそわなかったので、庶民からは逆に喝采をあびるところがあった。
小説の話とこの落語の噺では細部が違っています。円生が落語としての噺に直したのでしょう。
■火附盗賊改め:市中を巡回して、火災を予防し、盗賊を逮捕し、博徒の考察(探索)をつかさどる役。
この職は、初め、盗賊改めと火附改めとに分かれていた。
盗賊改めは寛文5年(1665)10月に先手頭の水野小左衛門守正が初めて兼務で任命された。
それから下って天和3年(1683)正月に火附改めが設けられ、これも先手頭の中山勘解由直守に兼務させた。
この職は、先手頭から選ばれた者が兼職するきまりとなり、毎冬、火事の多い10月から3月の間は、もう一人の先手頭を任命して補助させ、これを加役と呼んだ。で、年間をとおして勤めている者を本役と称した。したがって、世間で火盗改めのことを加役と呼んでいるのは誤解です。
この職は、本来は町奉行所の事件を代行するものだったから、非違の検挙と糾弾、科刑の裁定、そのほか一切の基準は全て、町奉行所が定めているところに準ずるように決められていた。
「もともと火付盗賊改方というお役目は、無宿無頼のやからを相手に、めんどうな手続きもなく規則もなく刑事にはたらく、いわば軍政の名残をとどめる荒々しき役目でござる。」と作者は平蔵に語らしている。
役宅は天保14年(1843)の頃、清水門外(内藤伝十郎屋敷跡)にあり、その敷地内に仮牢(詰子小屋という)、白洲、長屋下腰掛、内腰掛、訴所などを設けることは奉行役宅と異ならなかったし、配下の与力・同心も事務を分掌してお頭を補助した。その人数は、与力は5,6騎から10騎、同心は30人から50人が通例であった。
この職、町奉行に次いで市民の上に威権があった。しかし、持ち出しが多く、家が傾くとも言われた。
■白浪:盗賊の別名を白浪という。語源は中国で、紀元前220年の三国時代、黄巾賊(こうきんぞく、頭に黄色の布を付けた盗賊)の乱が、収まった後もその残党で山西省汾城県の東南、白波谷(はくはこく)にこもった張角(184没)が洛陽を脅かしたので、これを白波賊と称した。それが日本に伝来し、白波がシラナミと発音され白浪となった。
白浪物とは、盗賊を主人公とする芝居、小説、講談、などの事。白浪作者として有名な河竹黙阿弥(1893没)は、幕末の世相を背景として、歌舞伎役者の四代目市川小団次(1866没)のために、強盗、殺人、巾着切、盗賊、ゆすり、たかり、無頼漢、毒婦などを主人公にした物語を劇作し、上演された。これが好評で世人の共鳴を得て、小団次を白浪役者とも言う。黙阿弥は「白浪五人男」、「島鵆月白浪(しまちどりつきのしらなみ)」などの有名な狂言を書いたので、白浪作者と言われた。講談では白浪物を語って好演した松林伯円(しょうりん_はくえん。1855没)を泥棒伯円と称した。
2.長谷川平蔵邸跡 (墨田区菊川3-16)
墨田区教育委員会が平成10年11月に建てた、長谷川平蔵・遠山金四郎屋敷跡の説明版によると、
この一帯は江戸時代火付盗賊改役・長谷川平蔵や江戸町奉行・遠山金四郎が暮らした屋敷跡です。
長谷川家は家禄400石を受けていた旗本でした。平蔵宣以(のぶため)19歳の時、明和元年(1764)、父平蔵宣雄(のぶお)屋敷替えにより、築地から本所三の橋通り菊川の1200坪余りの屋敷に移りました。宣以は火付盗賊改役として通例任期2~3年のところ、没するまで8年間在職し、盗賊逮捕に実績を上げた。池波正太郎の鬼平犯科帳で当時の様子を活き活きと描いています。また、職業訓練をもって社会復帰を目的とする石川島の人足寄場を提案、実現させました。寛政7年(1795)病の為に、50歳で本所の屋敷で没しました。
その後、弘化3年(1846)孫の四代目平蔵の時屋敷替えになり、江戸町奉行遠山左衛門尉景元(遠山金四郎)は江戸北町奉行に天保11年(1840)に任命されました。一時解任されたが老中水野忠邦失脚後の弘化2年(1845)3月再び南町奉行として就任。以後、名奉行の名を残す評判を集め、「遠山の金さん」として浪曲、講談に登場する事になる。
この地は、江戸町人感覚にも通じ、治安に貢献した二人のゆかりの地です。
3.松寿院(
しょうじゅいん)門前
(寿松院=台東区鳥越2-13)
参謀格の前砂の捨造が小さな花屋を開き住んでいた所。
鳥越・松寿院というお寺は(噺の中の)架空のお寺で、実在はしません。しかし鳥越には「寿松院」(壽松院)という文字をひっくり返した大きなお寺さんがあります。このお寺さんを意識
(モデルに)して、実在の名前を使わずに、フィクションの世界ですから架空の寺名としたのでしょう。
隣には松寿院と名前の似た「長寿院」と言うお寺さんも有ります。
■根津門前:料理茶屋「すすきや」が有った所。夜兎角五郎・角右衛門父子が住まっていた。根津神社(文京区根津1)の門前。根津神社は落語75話「札所の霊験」で紹介したツツジで有名な神社。
4.広徳寺前 (台東区東上野4丁目 台東区役所跡)
■広徳寺(こうとくじ):この稲荷町広徳寺南側門前の道を広徳寺前と言った。この道は現在の駒形橋通り(浅草通り)に合致します。落語「双蝶々」の長吉が奉公に行った山崎屋はこの近くにあります。
この北奥に万年町が有ります。
広徳寺は関東大震災後、練馬区桜台6丁目20に移転しています。
廣徳寺は臨済宗大徳寺派のお寺で、台東区東上野にあったのが、大正2年の関東大震災を受けたあと、この地に2万坪の(約6万6千㎡)の土地を求めて移ってきた寺である。最初塔頭の円照院と墓地が移り、別院としたが、戦後、桂昌院や本寺も移ってきた(別院の円照院は秩父に移る)。この寺は元亀・天正(1570-92)の頃、岩槻城主北条氏房が義父太田三楽の菩提を弔うため小田原に建てたものを、徳川家康が神田に、後に下谷に移されたもので、諸大名、旗本の帰依するものが多く、塔頭も15を数え、「ビックリ下谷の広徳寺」と言われるほどであったが、幕末動乱と関東大震災で塔頭も桂徳院など4院に合併され少なくなった。寺の墓地には、柳生、前田(大聖寺)、小堀、織田、立花、小笠原、秋月、細川(谷田部)、市橋、関、松浦、真田(松代)、桑山、滝川、松平(会津)などの大名の墓が並んでいる。
練馬区教育委員会
■「松寿院門前から新堀端を菊屋橋に出、左に曲がり車坂に向かって歩いていた。」
角右衛門は鳥越の捨造の家から出て自宅の根津に向かった。その道順で、南北に走る新堀通り(菊屋橋から名前が変わって合羽橋通り)は江戸時代新堀という堀川が流れていた。今は埋め立てられて、ごく普通の道路になってしまったが
・・・。川端伝いに菊屋橋に出る。今は交差点名として残っていますが、過日は新堀川に架かった橋がありました。ここを左に曲がり、今の浅草通り(仏壇屋が多いので仏壇通り)を上野駅に向かって歩きます。上野駅にぶつかった所が車坂です。
車坂の少し手前右側に上野警察と並んで台東区役所があります。そこが、お幸さんのいた広徳寺前です。
当時は駅はありませんから、上野寛永寺の山(上野公園=上野の山)があり、その裾を回り込んで行くと根津に出ます。
■上野山下にある有名な高級料理屋「浜田屋」
車坂から左に回り込むと上野山下に出ます。現在の上野駅正面辺りです。そこに有った高級料理屋が浜田屋です。ここ山下には鰻屋、スッポン料理屋、など各種の料理屋が密集して華やいだ街を形成していた。
その先は両国広小路や浅草広小路(雷門前)に並び賑わった上野広小路です。
■下谷万年町にある乞食の溜まり
落語「黄金餅(こがねもち)」で紹介した、上野山下の北側、貧乏人が多く住んでいた(談志談)と言われた所。明治2年(1869)縁起がよいからと、山崎町から万年町に改称された。その後昭和の中頃町名変更になって、今は北上野一丁目及び東上野四丁目の一部に変わってしまいました。
舞台の鳥越から上野を歩く
台東区鳥越はご存じ鳥越神社(http://www004.upp.so-net.ne.jp/kab_ra/)があるので、その名が町名として付いています。蔵前
橋通りに面した鳥越神社は千貫神輿で有名な祭りを6月に齋行しています。その東隣の路地奥に松寿院ならぬ浄土宗壽松院が有ります。この門前に前砂の捨造が小さな花屋を開き、隠れ住んでいたのでしょう。
ここから東に路地を1本渡ると、新堀通りに出ます。遊郭吉原を囲む吉原田圃は低地にあったので水はけが悪く、大雨が降ると湿地帯になってしまいます。その為後年新しい新堀川を掘削しましたが、上手く工事が進展しませんでしたが、隅田川に住む河童のお陰で完成に漕ぎ着けます。その
新堀川は南北に流れ、隅田川に流れ込むのですが、今は道路となってその面影はありませんが、上流部分はその時の名前を取って合羽橋道具街となって賑わっています。
その新堀川に掛かった菊屋橋を左に、と言っても交差点名でしかありませんが、浅草通りに出ます。正面遠景に上野の山とJR上野駅が望遠出来ます。稲荷町の交差点を越えると左に下谷神社の大きな鳥居が見えてきます。その先、右
(北)側に上野消防署、上野警察署が現れ、その奥が台東区役所です。江戸時代には、ここに広徳寺という大きなお寺さんが有り、南側門前の道を広徳寺前と呼ばれていました。今の警察署がある辺りです。話の中では女乞食お幸さんが落とし主の現れるのを砂塵吹き荒れる中待っていた所です。
浅草通りの突き当たりが上野駅ですが、その右側一帯を車坂と呼び、左側を上野山下、略して山下と呼ばれていました。
上野警察(台東区役所=広徳寺跡)の北側に、朝顔市で有名な下谷鬼子母神があり、その下谷交差点の南側に万年町はありました。落語黄金餅に出てくる葬列の出発地点でもあります。
浅草通りが突き当たった道路が昭和通りで、上部には首都高速道路が走っていて、頭を押さえつけられるような高圧的な高架道路です。昭和通りは南に真っ直ぐ走って都心に行きますが、北には日光街道(4号線)と名を変えて延びていきます。旧の日光街道は上野駅南側のカードをくぐって中央通りと名を変えて南下し、日本橋に至ります。上野公園南側から御徒町に掛けては上野広小路と呼ばれ賑わったとこですが、今は道路工事の真っ最中で車はいつも渋滞で、歩道は人でイッパイです。人がイッパイなのは落語のメッカ鈴本演芸場があるからです。とは大袈裟ですが、今でも飲食店や商店街や歓楽街まである、盛り場です。
上野の山の西側には不忍池があり、その池にそって北に上っていくと、根津神社があり、その門前を根津門前と呼んだ町がありました。そこに主人公の角右衛門がすすきやと言う料理茶屋を女房にやらせていました。
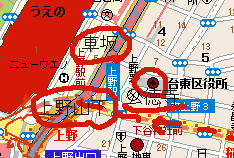 地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。
それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。
2007年1月記
次のページへ 落語のホームページへ戻る
|