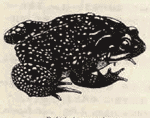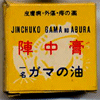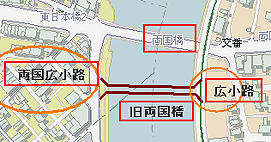�E寐䚄�i�Ђ������j�G���^�������킮���ƁB�]���āA���ɑ���Ȃ����̂ǂ��i��寁j���₩�܂����������킮���ƁB
�E���q���i�₵��j�G�R�R���q�̎킩���锒�F�̖��B�听���̓��E�����_�E�~���X�`���_�Ȃǂ̃O���Z�����]�G�X�e���B�Ό��E�O���Z�����̎�v�����B
�E�e�������e�C�J�G�I�����_��e�������e�B�i���a��B��������Ƃ�e���s�����B�h���n�܁A�����̂��A�C�n�A���E�\�N���Ɏg����B
�E�}���e�C�J�G�|���g�K����}���e�B�J���a��B���A����Ƃ鎉�B��p�̗��艄���p�̎��B
�E�������\�i�������炳�������āj�G�����͓����₮��ݍ��ɍ����ꍇ�̓����A�܂�g�̂ɒ������̓��g�̖ʁB����ɍ\�����ꍇ�̓��g�̉E���B���\�͂��̋t�̖ʁB
�E���̍����R�G�����Ă���̂ŁA�k�̒}�g�R�ƌ����Ƃ���A���̍����R�ƌ����ď��Ă��܂��B�����R�͍]�˂��猩�ē��ł͂Ȃ����̕��ŁA����u�V��ق��v�ōs�����Ƃ����
�A��d�ɊԈ���Ă��܂��B
�E�P�L�łP�O�O���G���ꕨ�ɔ��̊L���g���Ă����̂ł��傤�B���Ō����Ђƕr�܂��͂ЂƊʁB
�P�O�O���Ƃ́A�ꗼ���ꕶ�K�i�]�ˏ����A�S�ѕ��A�S,�O�O�O���A�����10,000���j�ł�����A�P�����W���~�Ƃ���ƂP�����Q�O�~�B�P�O�O���ŁA�Q,�O�O�O�~�i����łW�O�O�~�j�A�ȊO�ƍ������̂ł��B�ŁA��L�P,�O�O�O�~�i���S�O�O�~�j�ł��B����
�i�]�˒����j�\�o���P�U���A�V�n���\�o���R�Q���A�V�����P�O�O���ł����B
����\����@�i�䕺�����������@�@�u�����@�K�}�̍p��������v�@�@
�@
�Q�D�����L���H�i�����擌���{���A���������l�߁j
�@�]�˂ɍL���H�͂R���������āA���R���́u���J�L���H�v�A����O�́u�L���H�v�A�����Ă����u�����L���H�v������܂����B
�@����̑�i�P�U�T�V�E�U�葳�Ύ��j�͍]�˂̎s�X�̑唼���Ď����P�O���]�̎��҂��o�����B���̍ۂ��̕ӂ�œ�����������ďĎ�����҂������o�܂����B���̂��ߑΊ݂ւ̔��̕ւ�}��勴���˂���ꂽ�B���c��͕����Ɖ��������̋��E���Ȃ��Ă����̂ŁA�������̂��������ɂȂ����B�܂��A���Ėh�~�̂��ߋ��Ɍ�����������т��Ώ����n�Ɏw�肵�n�Ƃ����B���ꂪ�₪�čL���H�ɂȂ�A�����Ȃǂ�����Ő����ɂȂ��Ă������B
�Ύ��⏫�R�ʉߎ��͉��ݏ����͑����Ɏ�蕥��ꂽ�B
�@�]�˂œ��ɂP�痼�������鏊�Ƃ��āA���͊݁A�̕���A�g���ƉĂ̗����L���H�ɋ����������B������̊��y�X�ł������B�����L�������Ȃ牽���������������A���킢�̂���]�ˎO��L���H�̂ЂƂł��B
 ���}�g�R�G��錧���Ύs�B�}�g�R�͎R�����Q�A�����Ɉʒu����j�̎R�i871m�j�Ɠ����Ɉʒu���鏗�̎R�i876m�j����Ȃ�܂��B�̂���u���̕x�m�A���̒}�g�v�ƈ��̂���A���[�ɎR�������ɐF��ς���Ƃ��납��u����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���G�N�X�v���X�ł��ȒP�ɏH�t������s����悤�ɂȂ�܂����B
���}�g�R�G��錧���Ύs�B�}�g�R�͎R�����Q�A�����Ɉʒu����j�̎R�i871m�j�Ɠ����Ɉʒu���鏗�̎R�i876m�j����Ȃ�܂��B�̂���u���̕x�m�A���̒}�g�v�ƈ��̂���A���[�ɎR�������ɐF��ς���Ƃ��납��u����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���G�N�X�v���X�ł��ȒP�ɏH�t������s����悤�ɂȂ�܂����B
�@���[�v�E�F�C�A�P�[�u���J�[�������y�ɓo�R���y���߂܂��B�܂��A�n�C�L���O�R�[�X����������Ă���R�[�X�����ɂ́A�u�K�}�v�u�ٌc���߂�v�ȂǓ`���ɍʂ�ꂽ���E��������܂��B
���{�S���R�������Ƃ��Ⴂ�R�ł�����܂��B
�@
�R�D��寂̍p�i���܁]�́]���Ԃ�j
�@�K�}�̕���t���p�܂ɂ܂��ė������Ƃ�����p�B�̂����w�̍p��i�R���p�j�Ƃ��ėp�����A�₯�ǁE�ЂсE��������E�؏����Ɍ��\������Ƃ����A�哹�ɐl���W�߂č���t������ʔ����������B
�i�L�����j
�@���ł��}�g�R�̂��y�Y�Ƃ��ėL���ł��B
����寁i���܁j�̖�
�@��寁i���܁j�̖��̂������Ƃ́A�`���ɂ��ƒ}�g�R�̒����ɂ��钆�T���̏Z�E�E���_��l�����Ă̐w�ɓ�����Ƃ��ď]�R�A�폝�҂̎蓖�ĂɎg�����w���ǂ������ĕ]���ƂȂ�A���̌��_��l�̊炪�Ȃ�Ɖ�寁i���܁j�Ɏ��Ă����Ƃ��납��g�K�}��l�̖���h�Ƃ��Ă��Ă͂₳��A��X�w�K�}�̖��x�Ƃ��ėL���ɂȂ������̂ł��B��l�ʖ��g�}�g�̉�寏��R�h�B�܂�w�K�}�̖��x�̖��O�̗R���͊炪��寂Ɏ��Ă������߂Ŗ�������Ƃ��Ẳ�寂���Ɓi�Z���\�j�Ƃ͖��W�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�������
 �E�I�I�o�R�i�ʐ^
�B�O�U�N�P�O���B�e�j�A�ԑO���̂��ƁB�ԑO���Ƃ͎ԁi�����ԂłȂ����n�A���ɂ͐l�������唪�ԂȂǁj�̒ʂ铹�[�̗ւ̂قƂ�ɐ����鑐�Ƃ̈Ӗ��ŁA�I�I�o�R�Ƃ͑�t�q�ł��̗t���傫�����Ƃ̈Ӗ��B���Ԗ�I�ɂ͐��̗t�����Ԃ��ăJ�X������Ώ��A���ł��A��Ȃǂɗp�����邪�A�����ł͎ԑO�Ƃ����Ǝ�q�̎ԑO�q�̂��Ƃň�×p�ł����Ԑt�C�ۂɗp�����Ă���B�t���q�i�ԑO�q�i���Ⴚ�j�j�͗��A�܂�Z�L�~�ߖ�ɂȂ�B
�f�G�ȑ��̂悤�ɕ������܂����A�������ʂ̎G���ł��B
�E�I�I�o�R�i�ʐ^
�B�O�U�N�P�O���B�e�j�A�ԑO���̂��ƁB�ԑO���Ƃ͎ԁi�����ԂłȂ����n�A���ɂ͐l�������唪�ԂȂǁj�̒ʂ铹�[�̗ւ̂قƂ�ɐ����鑐�Ƃ̈Ӗ��ŁA�I�I�o�R�Ƃ͑�t�q�ł��̗t���傫�����Ƃ̈Ӗ��B���Ԗ�I�ɂ͐��̗t�����Ԃ��ăJ�X������Ώ��A���ł��A��Ȃǂɗp�����邪�A�����ł͎ԑO�Ƃ����Ǝ�q�̎ԑO�q�̂��Ƃň�×p�ł����Ԑt�C�ۂɗp�����Ă���B�t���q�i�ԑO�q�i���Ⴚ�j�j�͗��A�܂�Z�L�~�ߖ�ɂȂ�B
�f�G�ȑ��̂悤�ɕ������܂����A�������ʂ̎G���ł��B
�E�Ȃ���寂̓n�G�Ȃǂ̒��ނ�ߐH����̂ŃI�I�o�R�͐H�ׂ܂���B
���l�Z�i���낭�j�̉�寁i�������q�L�K�G���j
�@�q�L�K�G���G�J�G���̈��B�͔̂�債�A�l���͒Z���B�w�ʂ͉����F�܂��͍����F�A���ʂ͊D���F�ŁA���F�̉_��䂪�����B�畆�A���ɔw�ʂɂ͑�����
�C�{������B�܂��傫�Ȏ��B�������A�����L�ŔS�t��B����͓݂��A��o�āA��ō�����ߐH�B�~�͓y���œ~�����A���t����āA�r��a�Ɋ��V���ōג����R��̗�����Y�݁A�Ăѓy���ɓ����ďt���A���ĂɍĂяo�Ă���B���{�e�n�ɕ��z�B�q�L�B�K�}�B�K�}�K�G���B�C�{�K�G���B
�@��寂̎w�͎l�Z�i���낭�j�������Ŋ�`�ł͂���܂���B�ܖ{��������ُ�B�܂�O�r�ɂ͂T�{���̍������邪�މ����Ďl�{�Ɍ����A��r�͂T�{�̂����P�{��
�C�{�̂悤�ȓˋN������̂ŘZ�{�Ɍ�����̂����ʂł��B�i��쓮�����k�j
�@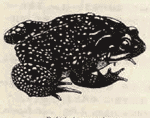 |
 |
�@ |
���l�ʋ��̔��E�����𗬂�
�@��寁i���܁j�̕���őf�Z���\�̌����Ŋw�ʂ���������r��搶�ɂ��ƁA���̂悤�Ȕ��ɓ���Ă������i�邱�Ƃ͏o���Ȃ������Ƃ̂��ƁB
�@�������A�_�œ˂�������ˑR�������Ȃǂ̎h����^����Ɩڂ̏�̏�����ᎂ̕�������狍���l�̏`����яo���B���ꂪ�ڂɓ���Ǝ������邵��寁i���܁j�����������ʂ��Ƃ�����A�Z���\�͂�����ł߂����̂ŋߔN�������i���͂Ȗ�����m�F����Ă��܂��B
����Ɓi�Z���\�j
�@��C�̉�寂̎����B�E�玉�B�����Q�r���镪�啨���ł߂���Ɓi�Z���\�j�́A�Â����炻�̋��S��p���~�S��Z�_�ۂȂǂɔz�����ė��p���Ă��܂������A�ߔN�����q�l�𗽂����ɍ�p����������܂����B���ɂ��Ǐ�������p�A�~����p������{���ɉ�寁i���܁j�̖�����Ƃ������Ă������t�i�₵�j�̌���͓������Ă��܂��B
�@�������Ȃ������̔��ƂƂ��Ē}�g�R�̓y�Y���X�Ŕ����Ă����寂̖��ɂ���Ƃ͓����Ă��܂���B
�@��O��寁i���܁j�̖�������Ă����}�g�_�Ђ̘b���ł͖{������Ɠ���̉�寁i���܁j�̖�������Ă������A���͋K���̂��ߎ~�߂Ă��܂����Ƃ̂��ƁB����w�w���p�E�ꖼ��寁i���܁j�̖��x��̔����Ă����R�c����ǂɂ��ƁA�}�g�_�Ђ̕�^��ňȑO�����Ă����L�k����́u��寁i���܁j�̖��v�͒��ׂ��烏�Z�����݂����Ȃ��̂Ŗ�肪����A������E�`�Łg��������p�h�����A�n���̖����̈Ӗ������߂āw��寁i���܁j�̖��x�̖��O�������̂ŕ]���͂����Ƃ̂��ƁB
�@�܂�͏��Ȃ��Ƃ�����ł���Ɓi�Z���\�j����́w��寁i���܁j�̖��x�͂��̐��ɑ��݂��Ă��炸�A��������L�V�܂̎R�c����ǂ��P�X�X�W�N�ɓ|�Y���Ă��܂��܂����B
�@���ݑ��Ђ̍���Ă���w��寁i���܁j�̖��x���y�Y���i���܂��̈��ĕt���j�Ƃ��Ĕ����Ă��܂��B
�@�u�����s��t��k�����x���v�@http://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_14.html�@���
���Ǝʐ^���p
�@
�S�D����������
�@
�@�Ǒ��͉��R�i�����j�ɏo���A����ł��������u�����������v�ł��B�Q�O�O�W�N�P�P���NjL
�@�~���͔��̒��Ŋy�������Ɏ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���낭�낭���G�O������e���Ă��鏗���̎L�тāA�����㏸���Ă����B�����̌��ł̓n�V�S��o�鏗�������邾���Ȃ�ł����ˁB
���͓��̌������G��������������A�ƂƂ��ɉ͓��̓����̂����A�Ԃ��Ȃ������ɖv����B�Z�\�̃I�V���̉��ɖт�A���Ă����͓��̂悤�Ɍ����āA�R�łȂ��ꂽ�Z�\�𑀍삵�Ă����B
���J�G�����G����͌Ăэ��݂̌��ゾ���Œ��g�͗ǂ�������܂���B���̐��͋��n�Ɛ��������������悤�Ȑ����ƌ����Ă��܂��B
���������̉��~�G�̂͏����ЁA���̖����_�Ђɂ悭�o�Ă����B�������̑��݂�m���Ă��܂����A�ŋ߂͌������܂���B���̌��������������ꗿ�������������A�Ⴂ��l�͓��肽�������B���䑕�u�͓��R��蕨�ł��������A���ɂ͐l�Ԃ������Ă�����̂������āA�����d�|���ɂȂ��Ă����B�����Ȃ��j�q�ɂ͉�����j�̈ꕨ�������������般�����B�ǂ�Ȓj�ł��u�M���`�v���Ɛ����オ�����B
���ׂ��i���j�G����ƒj������Ђ����肩�������̂�@���Ȃ���A�u�ׂȁB�E�E�E�ׂȁv�B�h�Ȃׁh���Ђ�����Ԃ�������A�h�ׂȁh���ƌ����B
����U�����U���i���j�G�ǂ�ȑ傫�ȉ����Ǝv���ē���ƁA���ɂ͒|�U���̑傫���̂Ə������̂����邾���B�����ĉ��Ƃ͌��킸�A�h�U���h�ƌ����Ă���̂��~�\�ł������B
����C�^�`�i���j�G�R�ŕ߂ꂽ���肾����ߊ��Ɗ댯����Ƃ̌���œ���ƁA�U�ڂ̔����Ă����Ă����Đ^�Ɍ����t���Ă���B�����u�傫�ȔɌ��A�I�I�C�^�`�B�͎R�Ŏ��邵�A�|���Ɗ�Ȃ��v�B
���l�H���l���G����̉~���̔��ɂ͏o�Ă��܂��A�����Ԃ�V��H�ׂ�Ƃ����B�����̒��͔��Â����������Ă�����ɁA����H�ׂ������U�炩���Ă���B�q����t�ɂȂ����Ƃ���ŗ�����Ԃ�V���A��o����A
���̘e�ɒu�����B���オ�u�������̉�ň�l�H�ׂĂ��܂��ĕ��̓L�c�C�A������l�H�ׂĂ��ǂ��̂����E�E�E�v�ƌ����ƁA�q�̒�����u���킢����������A��߂Ƃ��`�v�̐����|����A���q����S���̂������R�[���ɂȂ�A���̂܂܃]���]���Ə����̊O�ɁB
�ǂ��������_�}�V�ł��������A������]�˂̐l�B�͂����炩�Ɋy����ł����B
�@
| �@ |
 |
| �@ |
�g�t�̑c�J�k�J
���c�J���z�[���y�[�W��� |
�T�D�O�@�̐Έ�@�i����эO�@�̔n�j
�~���̔��̃}�N������A
�@���͍̐O�@����̐Έ��ƌ����āA�O�@���l���̑c�J�k�ɍs��������A��ň������Ă����k����ɐ����|�����B�u���@�A���ꂱ��A����Ȃ�����A�Ȃ�Ƃ��킯�Ă͂���܂����v�B
�k����́u�G�H����@���V����A���܂˂����A����@�_������B���ł͂Ȃ��Đ�����H�ׂ��Ȃ��v�B
�O�@����́u���悤���v�ƌ����āA���������Ă��܂����B���̌��J�ɏo������͂��ׂĐɂȂ��Ă��܂����B�O�@����ɘl�т����Ă��肢������߂�Ȃ��ƒf��ꂽ���A�ɖ�͂�^���Ă��ꂽ�B������Ĉ��ނƁw�ݖ�x�Ȃ݂̌��\���L��ƌ����B�������������̂�I�V�Ŕ����Ă����B
�@�q���U��Ȃ��悤�Ɏ��̘b�������A�i�O�@�̔n�j
�@�O�@����ɂ͂������@�͂�����B������̗[���A�����ςĂ���̂������O�@����u���̎ϓ������������Ă���Ȃ����v�Ƃ��肢�����B���[�͐ɂ����Ȃ��āA�u����͔n�ɐH�킷���̂ŁA�l�Ԃ��H�ׂ���̂łȂ��v�ƒf�����B���������ƍO�@����͗����������B
�@���Ă��̓������ɐH�킹��ƁA�ӂ��������̐g�̂��n�ɂȂ��Ă��܂����B���������[���A���������āA�O�@����ɒǂ����A������̒ۂɂ�����܂��āA�u���V���܁A�����ĉ������A�������Ɨ܂𗬂��č��肵���v�B�O�@��������킢�����ɂȂ��āA���̉Ƃɍs���ƁA�Ƃ̒��ɎȂ��ꂽ�n���߂����ɂ�������ł����B
�@�n�ɂȂ�������̑O�i�ݏo�ŁA����T���T���Ɖ�������ŁA
�����ɐ^���閧�̎���ƂȂ����B
�@���̖@�͂͂����ւ�Ȃ��̂ŁA�����炪�܂邭�Ȃ�A�猨�ցA���ɑO������ɂȂ�Ƃ�������ɁA��̂ق����炾��ɁA�l�Ԃ̎p�ɂ��ǂ��Ă܂���܂��B
���[�����q�݂Ȃ��猩�Ă���ƍ��A���傤�ǁA�w�\�̂������ʂ�߂��A
�@�͂����̊Ԃ̂Ƃ���܂ŋy�т܂����Ƃ��A
�u���A������Ƃ��V���܁A���A�����̂Ƃ��낾���͔n���݂ɂ��Ƃ��Ă�������v�B
�@
�@����̗��������
�@���������݁B���c��ɉ˂��闼�����̓����͗������L���H�ƌĂꂽ���ŁA���n�c�旼���̒n���ŁA����@�A�����w�A���Z�فA�]�˓��������قȂǂ�����A���o��������R����܂��B�������������A���唻�̈ߕ��A�C���̓X������܂��B�]�ˎ���ɂ�����@�𒆐S�ɓ�����Ă������ł��B
�@�������̐����A�����擌���{���ɂ��̕���h�����L���H�h���L��܂����B�����͉��ݏ������������сA�����ɘI�V���������W�܂�A�ɉ؊X�̗l����悵�Ă��܂����B���ɉĂ͖��Ӊԉ��オ��A��X���␅���肪�l�C�ł����B
�@�������A���̗����������ɂ͓����̓��킢�͂ǂ��ɂ���������܂���B�������A���ł���ɖx�A�k�ɖ���������܂��B
�@�h��寂̍p����h�͌������Ƃ���܂��A�q���̍��h�n�u�̖�����h���������Ƃ�����܂��B�}���V����n�u���͗L���ł����A�n�u�̓ł�����ꂽ�Ƃ����p��ł����A��寂̍p�Ɠ������\���������Ǝv���܂��B���X�Ƒ�������ɂ��q����͓B�t���ɂȂ��Ă��܂��B���R���͍őO��ł��Ⴊ��Ō��Ă��܂����B�ˑR
�u���̑܂̒������āv�ƁA���܂̒���`�������̂ł��B�����w�r�̂悤�Ȃ��̂������Ă��܂������A�m�F����O�Ɋ�Ȃ�����Ƒ܂͕����u�n�u�������ł���v�Łu�E���v�Ɠ����Ă����q���̎��ł��B���̈ꌾ�Ńn�u�̐M�p�������܂����̂ł��B���̌�A�A�I�_�C�V���E����肾���Ęr�ɂ��܂��āA�o�����ɂ��̓�p��h��ƃT�����ƌ��͎~�܂��Ēɂ݂͎~�܂����i�ƌ����܂����j�B�u���̓�p�͋ߓ����ɖ�ǂŔ̔�����邪�A�O��`���ł��邩��A�ʏ�́����~��������͔��z�́����~���B������~�����ƌ����Ă��A�܂���ǂł͔����Ă��Ȃ���B�v�ŁA�������͂��q����͔����C�\���ł��B�������Ȃ����������͂����Ĕ����Ă��܂��܂������A�ƂɎ����ċA���Ď���������A�o�J�ɂ��ꂽ���Ƃ�N���Ɏv���o���܂��B���́h�n�u�̖�����h�����̌㌩�܂���ˁ`�B
�@�䂪���[�a�͎�i�͌������Ƃ����BTV�Ń}�W�b�N������Ă��܂����A�q�������������ڂ��L���L�������Ȃ���y����ł��܂����A������l�������[�͂��炯�Ă��܂��B�����Ɓu�l���x�����猙�����v�ƁB�q�������̓V���[������ƌ����܂�����������܂���B�]�ˎ���̌�����������I�V���̃e�N�j�b�N���y�����̕���́A���݂͐����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@�u�哹�|�̐��v����̌��t�ɂ�����悤�ɁA�哹�|���Ȃ��Ȃ����͔̂���Ȃ��Ȃ������炾�ƌ����܂��B���K�I�ɖL�ɂȂ��āA������i���A�]�ˎ���̏������S�������Ȃ��Ă��܂����̂ł��傤���B�P���Ԓ��̃V���[���ς��������ŁA�i���͗̎������Ƃ͗ǂ����ӌ��ł��B
�@���Ђ̋����ʼn����ς�ƁA�Ō�ɃU���������ĉ��܂����A���Ђ˂������l�̊�̗ǂ��������܂��B
�@
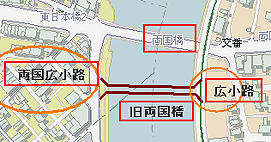 �@�@�n�}���N���b�N����Ƒ傫�Ȓn�}�ɂȂ�܂��B
�@�@�n�}���N���b�N����Ƒ傫�Ȓn�}�ɂȂ�܂��B
���ꂼ��̎ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�ȃJ���[�ʐ^�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�V�N�P�Q���L
���̃y�[�W���@�@�@�@����̃z�[���y�[�W�֖߂�
�@


 ���}�g�R�G��錧���Ύs�B�}�g�R�͎R�����Q�A�����Ɉʒu����j�̎R�i871m�j�Ɠ����Ɉʒu���鏗�̎R�i876m�j����Ȃ�܂��B�̂���u���̕x�m�A���̒}�g�v�ƈ��̂���A���[�ɎR�������ɐF��ς���Ƃ��납��u����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���G�N�X�v���X�ł��ȒP�ɏH�t������s����悤�ɂȂ�܂����B
���}�g�R�G��錧���Ύs�B�}�g�R�͎R�����Q�A�����Ɉʒu����j�̎R�i871m�j�Ɠ����Ɉʒu���鏗�̎R�i876m�j����Ȃ�܂��B�̂���u���̕x�m�A���̒}�g�v�ƈ��̂���A���[�ɎR�������ɐF��ς���Ƃ��납��u����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���G�N�X�v���X�ł��ȒP�ɏH�t������s����悤�ɂȂ�܂����B