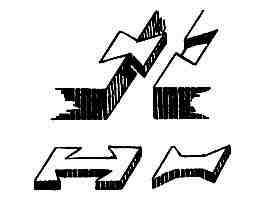|
落語「ちきり伊勢屋」の舞台を歩く
六代目 三遊亭円生の噺、「ちきり伊勢屋」によると。
麹町で名人の異名を取る占い師の白井左近に、「二月十五日正九つに死ぬ。」と宣言されたちきり伊勢屋の若旦那・伝次郎。積善を積めば来世は長生き出来るというので、貧しい人々や病人、心中を止めて施しをしていたが、切りを見計らい、冥土のみやげにと、道楽を始めた。
吉原でも遊び、芸者もあげるという、その遊びが派手でございます。歳が若くて、男っぷりが良くて、湯水の様に金を使うんですから、女の子にもてますが、十二月になると、そろそろ懐具合が危なくなってくる、田地田畑(でんちでんぱた)を売る、家を抵当に入れて金を借りる、この借りた金の返済期限が二月の晦日!どうせ二月十五日に死ぬんですから、返す気なんざありません。
一月は夢のように過ぎまして、二月になると店の者には十分な手当を出して暇をやる。二月十三、十四はお通夜という、仏様が生きているうちにお通夜をする。お通夜と言っても芸者、幇間をあげてのどんちゃん騒ぎ。いよいよ二月十五日。
暖簾(のれん)を裏返して簾(すだれ)をかける、忌中(きちゅう)の札を下げる。湯灌(ゆかん・遺体を棺に納める前に湯でふき清めること)をして風邪をひくといけないてんで、お湯に入って、経帷子(きょうかたびら・死者に着せる白い着物)を着る。首に水晶の数珠をかけまして、早桶(はやおけ・お棺)は黒檀(こくたん)、じかに入るとケツが痛いからてんで、中に布団が敷いてある。正九つ、伝次郎、早桶に入ります。
「窮屈だといやだから、大きめに作ったんだ、もう一人入れそうだ、お前、入らないか。」
幇間「ご遠慮します。では、どうか、ご無事でお隠れになりますよう。」
早桶のふたを打ち付け、枕団子にシキミの花をかざる。葬式らしくなりまして、幇間達が順にお悔やみを言う、芸者衆は泣き崩れる。
「おいおい!」
幇間「へ?誰か呼んだかい。棺の中から声がするね。」
「俺だ、俺だ。まだ死なないんだ、ちょいと煙草がのみたくなったんだ、棺に穴を開けて、キセルを突っ込んでくれ。へへへ、末期の煙草てのはうまいね。お前達、白足袋と黒足袋がいる、白足袋に揃えるがいいじゃねぇか。袴の後ろが下がってるよ、袴ぐらいちゃんとはけねぇのか。そんな所に土瓶を置いておくと出棺の時けつまづくぞ!」
やかましい仏様で・・・今の時刻で午後一時ごろ出棺、お寺につきまして、お坊さんにお経をあげてもらう。いよいよ棺を埋めようとする、酔ったやつが、足を滑らせたんで、棺を落と
した。
「いてぇな、気をつけろ。」、幇間「へぇ?まだお隠れじゃないんですか? 日を間違えたんじゃ?」、「たしかに、二月十五日九つと言われたが、始めてなんで伸びたかな?」
幇間「お産じゃありませんよ。」、「まだ、埋めちゃいけねぇ、腹が減ったから鰻でもあつらえてくれ。おい、ちょっと開けてくれねぇか、手水(ちょうず・トイレ)に行きてぇ。」
どうしても死にません、お寺に話しをして、先に納めた金から五十両借りましたが、帰る家もございません。方々を転々としましたが、その年の十月にはひどい有様で、乞食同様と言う。高輪の大木戸へ来ると、往来で人相、手相を見ている白井左近に再会する。お前のお陰でえらい目に逢ったと殴りつけると、左近は伝次郎が人助けをしたので人相がすっかり変わり、今度は八十歳以上長生きをすると言う。
左近から、迷惑をかけたと一分の金をもらい、品川へ行けば運が開けると言われた伝次郎、品川で幼なじみの伊之助に会う。伊之助は道楽が過ぎて親父に勘当され、品川新宿(しんしゅく)の貧乏長屋で、日傭取(ひようとり・日雇いの労働)をしていると言う。伝次郎はそのまま、伊之助の長屋へ転がり込み、大家の勧めで、二人で駕籠かきを始める。
芸人らしい風体の客をつかまえ、土蔵相模(どぞうさがみ・当時、品川で有名な遊女屋)までの約束で乗せるが、始めて人を乗せた駕籠を担ぐんで、重くてままにならない。腹が減ったからと、途中のおでん屋へ入り、おでんで一杯、金がないので、寝ている客を起こし、勘定を払ってくれる様に頼むが、駕籠賃の前払いなんて聞いた事がないと断られる。
客「いったいどの位来たんだ。」、「乗せた所から一丁(いっちょう・約109m)ばかり。」。客「冗談じゃねぇ、こんな駕籠に乗ってられるか、履き物を出せ。」、「乗せた所へ忘れて来た。」
客「なんだと!」、「おい、一八(いっぱち)、俺の顔を忘れたか。」、客「ん・・・、これは!ちきり伊勢屋の若旦那、どうなすったんですか。」
客は道楽をしていた時、贔屓にした幇間の一八。伝次郎は、二月十五日にとうとう死ななかったこと、そして、落ちぶれて駕籠屋になったことを話し、一八に昔贈ってやった着物と金をもらい受け、翌日、着物を金にしようと、藤屋という質屋へ行くが断られ、外に出ると番頭に呼び止められた。
「伝次郎さんではございませんか?手前どもの主人がお会いしたいと申しますので、ちょっとこちらへ。」
案内をされた所へ出て来たのが、歳が四十をちょっと越した品の良い婦人と十七、八の器量の良い娘。「お久しぶりでございます。」
聞くと、以前に赤坂の食い違いで、伝次郎が百両恵んで首くくりの心中を助けた母娘。あの百両のお陰で、借金の返済も出来、今では藤屋と言う立派な質屋を経営するようになった、どうか、娘を伝次郎の嫁にして、店を継いでもらいたいと言う。
この娘と夫婦になり、ちきりの暖簾をかけて、立派に家を再興すると言う、積善の家に余慶あり、ちきり伊勢屋でございます。
長文、最後までお読みいただき有り難うございます。テープから起こしていますが、円生約2時間の長講でした。お読みいただいた方もお疲れの事と思いますが、起こした私も疲れました。はい! 歳ですから。(誰ですか。そーだ、なんて言ったのは。もう遊んであげないよ)
1.江戸の刑罰について
江戸では、死刑でもランクが六つあり、重い順に・・、
|
鋸挽(のこぎりびき) |
首だけ出した状態で生き埋めにし、首を竹の鋸で挽いた後、磔。 |
|
磔(はりつけ) |
公開の刑場で十字に組んだ柱に縛り、槍で両脇の下から反対の肩へ突いて殺す。 |
|
獄門(ごくもん) |
牢屋敷で斬首後、公開の刑場で首をさらし、遺体は刀の試し切りにする。 |
|
火罪(かざい) |
放火犯に適用、公開の刑場で柱に縛り、薪で焼き殺す。 |
|
死罪(しざい) |
牢屋敷で斬首、遺体は刀の試し切り。 |
|
下手人(げしゅにん) |
牢屋敷で斬首、遺体は親族に渡され、葬儀、埋葬が許される。 |
わ~、痛そ~。痛いじゃなく、死刑ですよ。こんな殺されかたされるなら、歯医者に行っていた方がどんだけマシか。
それ以下の刑罰が、重い順に
|
遠島(えんとう) |
伊豆七島の八丈島・三宅島・新島に送られる。佐渡島は最悪の島流し。 |
| 重追放 |
犯行地・居住地・江戸十里四方から追放。 |
中追放
|
犯行地・居住地・武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道・木曾街道・日光街道に立入禁止。 |
| 軽追放 |
犯行地・居住地・江戸十里四方・京都・大阪・東海道・日光街道に立入禁止。 |
|
江戸十里四方追放 |
日本橋を起点として、五里以内から追放。 |
|
江戸払い |
品川・板橋・千住・四谷・本所・深川の(江戸切り絵図内)区域から追放。 |
| 所払い |
居住する町村から追放。 |
|
敲(たたき) |
牢屋敷門前で公開で50回(敲)か、100回(重敲・おもたたき)ムチでたたく。 |
|
晒し(さらし) |
公開の晒し場の柱に縛って晒す。 |
|
非人手下(ひにんてか) |
非人に身分を落とされる。 |
|
押込(おしこめ) |
罪の重さにより、20~100日の自宅謹慎。 |
手鎖(てじょう)
|
罪の重さにより、30・50・100日間、手錠の様な拘束刑具で両手を縛ったままの状態で生活する。 |
|
過料(かりょう) |
罰金刑。 |
|
叱り(しかり) |
奉行所のお白洲でお奉行様が叱責する。 |
となります。
死刑にする場合も、執行前に裸馬に乗せて市中を引き回したり
(八百屋お七の例)、遠島などの場合は家財が没収されたりします。刑が決まるまで、小伝馬町の牢屋に収監されますが、今の懲役に当たる刑罰はありませんでした。罪を犯した人に、
幕府の金を使って長期に渡り更生させるなんて、余裕がなかったのです。
人一人殺(あや)めれば死刑、十両以上盗めば死刑、十両以下でも再犯は死刑、巾着切り(きんちゃっきり=すり)も三回捕まると死刑。現代と江戸、どちらが良いのか分かりませんが、現代で約100万円盗むと死刑と言うことで、現代の様に犯罪者の人権を重視するより、江戸は被害者の救済や犯罪抑止の方を重視したのです。死刑も重罪の場合、犯罪抑止を目的とした鈴が森や小塚っ原で公開処刑や、切り落とされた首を政治犯や重罪人は晒しものにしたり
しています。結果、江戸は非常に犯罪の少ない、治安の良い街でした。
2.江戸払い
伝次郎が白井左近と再会するのは「高輪の大木戸」。現在の都営浅草線の泉岳寺駅から三分程の所に、国の指定史跡「大木戸跡」があります。享和年間(1801~1803)に伊能忠敬が全国測量に出発するとき、起点にしたのがここで、江戸と東海道との出入口にあたるところ、大木戸から中が江戸となります。
白井左近は伝次郎の死相を見たと言う罪で、家財を没収され、江戸払いとなり、江戸に近いが江戸ではない高輪のエリアで、家財もないので大道易者をして生計を立てていた、と言うことになります。
江戸払い、ですから品川より南になりますが、実際は江戸の境界は高輪の大木戸だったのです。岡っ引きの勢力(警察・行政権)が及ぶ範囲はここまでだったので、その境界間近で生計を立てていたのです。
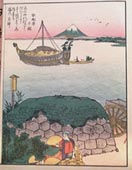 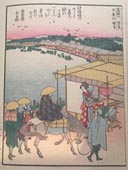 江戸時代の高輪大木戸 江戸時代の高輪大木戸
3.二月十五日正九つ
伊勢屋伝次郎が死ぬと言われた日時。今年(2005年)で言えば3月24日、正午(12時)。善行を施したので死期を外してしまいました。
■白井左近の易;
白井左近は当代随一の易者。失せ物の行方から客の人相を見て剣難を当てるなど、あまりにもよく当たるので左近の家は千客万来のにぎわい。
ある夏の夕刻、伊勢屋伝次郎は白井左近に縁談について占ってもらう。左近は伝次郎の人相を見て、死期を占う事は御法度であったが、あまりにもハッキリと出ていたので、「あなたは来年の二月十五日に死ぬ。これだけはっきり出ているので申し上げる。
だから嫁はめとらない方が良い。」と言う。「先代が乞食伊勢屋と陰口をたたかれるほどあくどい商売をして人を苦しめてきたからだ。」とも言う。また、「助かる方法はないが、困っている人に施しをすれば、来世は長生きできる。」と告げる。
結局、名高い白井左近の言うことを信じた伝次郎は番頭の藤兵衛と相談し、商売そっちのけで、施しを始める。病人・貧乏人の噂を聞きつけては、駕籠に乗り訪ねて行って金を施す。ある日、駕籠に乗り疲れた伝次郎は、駕籠を降り歩いて帰る途中、食い違いで首吊りをしようとしている母娘に出会い、百両の金を施して心中を思いとどまらせる。・・・と、噺は始まります。
あまりにも当たりすぎる易を立ててもらうと、その後の生き方に混乱が生じます。当たるか当たらないか、迷うぐらいが適当なのかも知れません。それでは週刊誌の星座占いと同じになってしまいますが、それが正解なのかも知れません。
4.ちきり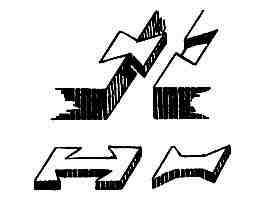
ちきり‐じめ【ちきり締】;木または石を接ぐため填(ウ)め込むもの。両端が広く、中がくびれて狭い。
ちぎり‐き【乳切木】;両端を太く、中央を少し細くけずった棒。元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。ちぎり。
文・右画 広辞苑より
ちきり;1
織機の部品の一つ。中央が細くくびれた棒状のもので、縦糸を巻きつけるのに用いる。緒巻(おまき)。輪鼓(りゅうご)。
2
紋所の名。ちきりを図案化したもの。ちきり、四方ちきりなどの種類がある。
3
「ちきりじめ(ちきり締)」の略。木または石材などをつなぐ際、その合わせ目や割目にはめてかすがいにする物。両端は広く、中央部がくびれて狭くなっている。ちきり。
小学館・国語辞典より。
ちきり;ちぎ‐ばかり【杠秤・扛秤・杜斤】、近世、1貫目以上の重い物の目方を量るのに用いた大桿秤(サオバカリ)。ちき。ちぎ。ちきり。ちぎり。
とも広辞苑に出ていますが、紋所にしていたと言うので、秤ではなく、かすがいに使うものの事でしょう。
 |
 |
 |
 |
 |
| 千切崩し |
千切菱 |
四方千切 |
三つ寄せ千切 |
隅切り千切 |
円生は「ちきり」と言っていますが、本によっては「ちぎり」と表記しているものもあります。どちらにしても、前世からの因縁、ゆかり、両者を結ぶもの
の意味と捉えられるでしょう。
今回の「ちきり」は伊勢屋の屋号で、『ちきり伊勢屋』とはイイ屋号です。その紋所は上のどれかだったのでしょう。
5.赤坂の食い違い(
食違見付跡。千代田区紀尾井町6、ホテルニューオオタニ北側)
ホテルニューオオタニ北側から赤坂御所脇を通る外堀通り(紀之国坂)に抜ける所が赤坂の食い違いです。
江戸三十六見付の内一番高い地点にありました。石塁を交差させて敵の侵入を防ぐ造りになっていたので食い違いと言います。
都心の一等地なのに今でも薄暗く人通りも少なく寂しい所で、円生の言う「首くくりの名所」だと言うのはここです。
紀尾井町は江戸時代ここに紀伊、尾張、井伊三家の屋敷があったので頭文字を取って地名になりました。上智大とホテルニューオオタニを挟む坂が「紀尾井坂」、その最上部の石垣の所が「食違見付跡」です。
明治7年(1874)1月14日夜、右大臣岩倉具視が馬車で帰宅途中、この食違見付で数人の刺客に襲われました。負傷したが、馬車から溝に転落。それを見た刺客は暗殺が成功したと思い込み引き上げていった。出来たばかりの警視庁の捜査で犯人は逮捕されたが、時の政府は大騒ぎになった。この事件を「食違いの変」と言います。
その4年後、それ程離れては居ない所で、「紀尾井坂の変」が起こります。
明治11年(1878)5月14日朝、麹町清水谷において、赤坂御所へ出仕する途中の参議兼内務卿大久保利通が暗殺されました。現在の内閣総理大臣にも匹敵するような立場にあった大久保の暗殺は、一般に「紀尾井坂の変」と呼ばれ、人々に衝撃を与えました。明治21年5月「贈右大臣大久保公哀悼碑」が近くの紀尾井町清水谷公園に完成しました。(千代田区教育委員会文化財説明板より)
紀尾井坂を下った所、清水谷公園には高さ6.3mもの「贈右大臣大久保公哀悼碑」が建っています。
舞台の食い違いを歩く
”食い違い”不思議な地名でまさかそんな名前が江戸の街に存在するなんて、調べる前には想像だにしませんでした。その食い違いに出掛けましょう。
赤坂見附で地下鉄を降ります。前の弁慶堀に架かった弁慶橋を渡ります。右は赤坂プリンスホテル(元・紀伊邸)、左はホテル・ニューオオタニ(元・井伊邸)、それも高層ホテルでその谷間を抜けるように北上するのが、今歩いている”紀尾井町通り”です。まもなく右に”清水谷公園”が現れます。この公園の中央部に人々に衝撃を与えた大久保利通暗殺があった「紀尾井坂の変」の慰霊碑「贈右大臣大久保公哀悼碑」が建っています。
公園を通り越すと直ぐに道路は突き当たります。左に曲がって、上り坂になります。この坂が”紀尾井坂”と言います。短い坂で直ぐにホテル・ニューオオタニに入っていく小さな交差点に出ます。そこが”食い違い見付跡”です。右むこう側の小高くなった石垣に”食違見付跡”の標柱が立っています。細い道をつたい石垣の上に登ると回りがよく見えます。
足元に埋め立てられた外堀、その正面に赤坂御所の緑と、手前の塀づたいに走る紀ノ国坂(外堀道路)が見えます。左側はホテル・ニューオオタニ、右側は上智大学
(元・尾張邸)、後ろは今上がってきた紀尾井坂が見えます。
食違見付跡は今でも細い山道のような植え込みと、その間を抜けるように走る小径が、当時の様子をそのまま味わう事が出来ます。すれ違う人に「こんにちは」と、山道で交わす挨拶がおかしくないような静けさ
と雰囲気です。「心中の本場は向島、身投げをするのが吾妻橋、犬に食いつかれるのが谷中の天王寺、首くくりが赤坂の食い違い」と言った円生が正しいようです。
 地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。
それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。
 |
赤坂の食い違い(食違見付跡。千代田区紀尾井町6、ホテルニューオオタニ北側)
上智大とホテルニューオオタニを挟む坂が「紀尾井坂」、その最上部の石垣の所が「食違見付跡」です。
|
 |
「贈右大臣大久保公哀悼碑」(紀尾井町清水谷公園内)
「紀尾井坂の変」で暗殺された大久保利通を哀悼し碑が建てられました。
|
 |
高輪の大木戸跡(港区高輪2-19
第一京浜国道沿い)
享保9年(1724)現在地に構築され、江戸の南の入口として道幅約6間(10m)の旧東海道の両側に石垣を築き夜は閉めて通行止めとし、治安の維持と交通規制の機能を持っていた。
旅人の送り迎えもここで行われ、付近には茶屋などもあって、品川宿に至る海岸の景色も良く月見の名所でもあった。(上記浮世絵参照)
江戸の後期には木戸の設備は廃止され、現在は海岸側に幅5.4m、長さ7.3m、高さ3.6mの石垣のみが残されています。
四谷大木戸は名のみを残すだけで、高輪大木戸跡は東京に残された貴重な史跡となっています。
伊能忠敬は日本全図を作るに当たり、ここを基点にした事でも有名です。
|
 |
土蔵相模(品川新宿)
写真は現在の旧東海道にある土蔵相模跡に建つコンビニです。右側の道路が旧東海道で、左側は緩い下り坂になっていて、品川の海になります。現在は埋め立てられて、その先まで陸が続きます。通りの手前に落語「居残り佐平次」や「品川心中」の舞台「島崎楼」が有りました。 |
 |
麹町(こうじまち。千代田区麹町)
サル旦那が住んでいたという。地下鉄「麹町駅」。新宿通り、麹町の街並み。
|
2005年5月記
次のページへ 落語のホームページへ戻る
|
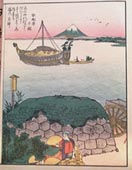
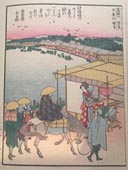 江戸時代の高輪大木戸
江戸時代の高輪大木戸