|
落語「首提灯」の舞台を歩く
六代目 三遊亭円生の噺、「首提灯」によると。

A
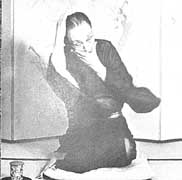 B B
 C C
 D D
 E E
|
博打で懐の暖かい江戸っ子の酔っぱらいが芝山内を通りかかった。最近辻斬りや追いはぎが出るのでぶっそなので、景気付けに大声で通り抜けようとしたら武士に呼び止められた。
辻斬りか追い剥ぎかと一瞬ビックリしたが、その様でもなさそう。安心して酔っぱらった勢いで武士に反抗し毒づいた。追いはぎではなく「麻布にめえるにはどうしたらいいか
」と聞いてきたが、道の聞き方を改めて説教し、さんざん武士に反抗する。切りたかったら、切りやがれと悪口狼藉。その上、痰を紋服に吐きかけて悪口を並べる始末。
武士の顔色が変わると改めて、もう一つ吐きかける。さすがの武士も我慢が出来ず、雪駄をならして後ろから腰をひねって、「えぃ!」。チャリーンと鞘に収める早業は目にも止まらぬさまであった
。(写真A) 謡曲を謡いながら去っていった。
それでも後ろ姿に毒ずく酔っぱらい。(首が徐々に横向いていく)、品川の女郎との一人のろけをしていると(また首が徐々に横向いていく)、俺の首はこんな建付が悪くは無いんだが。声がかすれて、「どこからか声がもれているぞ」。ガックと首が落ちそうになる所をかろうじて両手で直した。(写真B)
首筋を触って血が付いているのを見つけ、「野郎、やりやがったな」。(写真C)
そこに近くで火事が出た。人が出てきて混み合ってきた。弓張り提灯を持った人が駆けて来るし、「じゃまだ、じゃまだ!」とぶつかる者も出始めた。こちとら壊れ物を持っているのだ、(写真D)
落っこどしては大変と自分の首を
提灯のようにヒョイと差し上げ「はいゴメン、はいゴメン、はいゴメン!」。(写真E)
(写真は文藝春秋デラックス古典落語と古川柳「日本の笑い」 昭和49年11月号より
円生師) |
前回の噺「試し斬り」はこの噺のマクラです。今回は本題部分をクローズアップしています。どの落語家さんも粗筋は同じです。
この噺は典型的なSF的な噺で、落語的な噺の典型でしょう。
この噺には原話があって『軽口五色帋(ごしきがみ)』(安永3年・1774)より概略を紹介すると、
有る所に盗人入りける、亭主ぬからぬ男にて、用意の腰の物、鯉口切って待ち構えているとは知らず、居間の襖を開けて入るやいなや、首を打ち落とされてしまった。落ちたる首を拾い上げ、懐へねじこんで、こけつ転びつようよう門へ出るが、何が真の闇ではあり首はなし。一向一足も歩まれねば、懐より首を取りだし、髻をつかんで差し上げ、「ハイ ハイ ハイ」。
1.首提灯について
円生は芸術祭参加作品として「文七元結」を熱演しましたが、反応はなく、それではと東横落語会で普段より短くこの「首提灯」を演じて早々に次の会場に向かってしまいました。そのときの噺で芸術祭文部大臣賞を受賞しました。弟子が聞いていて文七元結は凄い出来であったと言うことですが、審査委員との感性の差が有ったのでしょう。円生自身も驚いていました。その後この首提灯はあまり高座に上げなくなりました。その理由は後に出来の悪いそれを聞いた人たちが、「あんな出来で貰ったのかと、言われるのが嫌で」と語った。
円生が亡くなってもう、二十三回忌になるようです。昭和54年(1979)9月没。もうそんなに昔のことなんですね。残された”音”を聞いていると、その事が嘘のように感じられます。
オチは談志や志ん朝は火事場でこの後に、世話になっている御店の見舞いに駆けつけて、弓張り提灯をかざしている他の見舞客の後ろから自分の首提灯をかざして、「”八五郎”でございます
」。と演っていた。志ん朝は彦六の正蔵から教わったと言っています。
この噺は火事の噺で季節は冬の噺です。志ん朝は未だ上手く演じられないが季節が冬だけのものだから演じる回数が少なく、なかなか上手くならないと、こぼしていた。
2.芝山内(芝増上寺境内)
第30話「鈴振り」で訪ねていますので、そちらもご覧下さい。
増上寺縁起(東京都港区芝公園4-7-35) 鈴振りより再掲載
浄土宗の七大本山の一つ。三縁山広度院増上寺(さんえんざんこうどいんぞうじょうじ)が正式の呼称。開山は酉誉聖聡。江戸時代の初め源誉存応(げんよぞんのう)が徳川家康の帰依(きえ)を受け、大伽藍(がらん)が造営された。以後徳川家の菩提寺として、また関東十八檀林(だんりん)の筆頭として興隆した。さらに、江戸時代総録所として浄土宗の統制機関ともなった。戦災によって徳川家の将軍やその一族の御廟(ごびょう)は焼失した。焼失をのがれた三門(さんもん)・経蔵(きょうぞう)・御成門(おなりもん)などを含む境内は、昭和四十九年(1974)完成の大本堂とともに、近代的に整備された。(ホームページより)
元増上寺のお宮であった「芝東照宮」は神仏分離令により隣の敷地に現在も立派なお社を構えています。
3.弓張り提灯
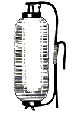 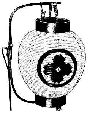 鯨のひげや竹を弓のように曲げ、火袋をその上下にひっかけて張り開くように造った提灯。弓のところを持って使う。
鯨のひげや竹を弓のように曲げ、火袋をその上下にひっかけて張り開くように造った提灯。弓のところを持って使う。
持って駆けだしても消えないので、捕り物や火消しが使った。左図の正面に”御用”と書かれた御用提灯は有名です。
(図は広辞苑および小学館国語辞典より)
舞台の芝公園を歩く
芝山内は浅草、上野、飛鳥山、深川などと並び明治になって公園と言われた。芝公園(芝山内)には芝増上寺や東京タワー、ボウリング場、プリンスホテル、芝東照宮などが立ち並んでいます。
公園南部の丸山と庭園は当時の静けさと寂しさを感じることが出来ます。丸山は今でも登れますが、夜登るのにはちと寂しく一人では遠慮したくなります。二人では?・・・、相手を見てからね (^_-)
武士が浅草から麻布に行く帰り道が分からなくなったので、道順を聞いています。突っ張って毒づかなくても舞台の直ぐ西側が麻布です。馬鹿にしながらアゴでそっち、と言えば提灯のような首にはならなかったのにネェ。
今日はみなと区民まつりがここ芝公園で開催されていました。JAZZ IN
TOKYOや物産展や模擬店が出て盛大に開かれていました。当然ながら、テントの模擬店では提灯を下げている店は見あたりませんでした。人出も凄く、増上寺では
光摂殿(こうしょうでん=僧侶の修行道場施設)で小倉遊亀、上村松篁をはじめ日本画の重鎮120人の天井画や襖絵を公開していました。これは祭り以上に価値がある物でした。
 地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。
公園に立っていた案内地図。
上からテニス場。道路を挟んでその下緑色が庭園、その右側が貝塚で古墳になっています丸山。庭園の下四角の枠の中が芝東照宮です。その下が建築中のプリンスタワーホテル、その下中央部分が芝増上寺です。右側に東京タワーが有ります。公園の下側に芝プリンスホテル、最下段緑色が庭園とみなと図書館が有ります。
(南北が逆になっています)
それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。
 |
芝山内(芝増上寺境内)
芝公園と言えば、この東京タワーと増上寺。秋の青空の下赤白のタワーと増上寺の屋根が時代を対比させます。
|
 |
増上寺山門
山門、増上寺の石柱、どれをとっても時代と大きさを実感させます。芝山内のもう一つのポイントです。
|
 |
芝丸山古墳
芝公園の南西部を丸山と呼ばれて小高くなっています。丸山の東南部に貝層があり、貝塚の一部と分かっているが有名な割には本格的な調査が行われていない。縄文時代後期の貝塚と考えられている程度です。
この丸山の上には前方後円墳の大型の丸山古墳が有る。これも、破壊、盗掘されて詳しいことが分かっていません。
長屋の花見で紹介した上野公園のすり鉢山と同じように、都内にも結構大型の古墳が有るものです。
|
 |
伊能忠敬記念碑
静かな丸山古墳の頂上部分に伊能忠敬を記念して碑がたっています。
伊能忠敬は晩年測量技術を学び日本全国を行脚して実測。日本で初めての日本地図を作り上げた偉人です。現在の人工衛星での測量から比べても誤差の少なさに驚きを隠せません。
|
2002年10月記
次のページへ 落語のホームページへ戻る
|

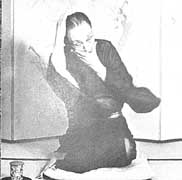 B
B C
C D
D E
E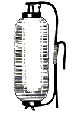
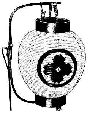 鯨のひげや竹を弓のように曲げ、火袋をその上下にひっかけて張り開くように造った提灯。弓のところを持って使う。
鯨のひげや竹を弓のように曲げ、火袋をその上下にひっかけて張り開くように造った提灯。弓のところを持って使う。




