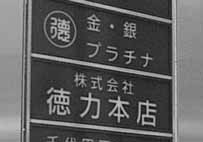|
落語「五貫裁き」の舞台を歩く
立川談志の噺、「五貫裁き」によると。
神田の三河町に家主の”多呂兵衛”、借家人の半端者の”八公”が住んでいた。この八公が人生立ち直ろうと奉加帳を持って町内を回ると、血だらけで戻ってくる。聞くと”徳力屋”に最初よったところ、番頭はたった3文しか付けない。怒ると主人が出てきて1文を付けた。怒ってけんかになって怪我をした。家主が理不尽さに怒り奉行所に願書をしたためて聞き入られ、大岡様の裁きになった。しかし、徳力屋万右衛門が裁きに勝って5貫文(5000文)の罰金。「それを毎日取り次ぎの徳力屋に1文ずつ持参せよ」と言う裁き。
翌日、八公がしおらしく1文を朝早くに徳力屋に持参。徳力屋は「ざまあみろ」と馬鹿にしながら受け取り、1文では買えない半紙に受け取りを書かす。徳力屋はその金を小僧に持たせ奉行所に持参するがなかなか役人が会ってくれず、やっとの事で会うと
、奉行に「万右衛門本人が名主と五人組が一緒に持参しろ」とおとがめを受ける。五人組にお願いすると費用はかかるし、本人が行っても一日がかりになって仕事どころの話ではない。
(サ
〜、大変徳力屋。面白くなってきた八公側連合軍。)
翌日も嫌がらせで朝の明ける前から1文を持参。また翌日も。ついには八公昼寝をして一晩中、今日の分、明日の分次の日の分だと寝かさない。たまりかねた徳力屋、やっと、事の重大さに気づき、示談にしたいと10両の金を提示するが、拒否。町内の名の知れた人が中に入り、100両と最初の目的の小さいながら表通りに八百屋を付けて、「これでどうですか」とでた。八公もこれを受けて示談成立。家主の知恵で八公の勝ち!
回りの人たちも、これを聞いて「徳力屋は偉いね」と噂をするようになった。いつか徳力屋の耳に入り「番頭さん、金は使うと人に喜ばれるね」と気づき施しを始め、徳力屋の評判は上がったが、金を使いすぎて店はつぶれ、八公は持ち付けない金を持ってずらかり、主人公達も死んでこの話を知っているのは、ここにいる寄席のお客さんと私(談志)だけになった。
別名「一文惜しみ」とも言う。円生が演っていた。
1.五貫文
罰金の五貫文は、既におわかりの通り、5,000文(=1両)。毎日返しに行くと、5000日、約13年8ヶ月。
徳力屋は大変な手間と時間、経費が掛かることに始めて気づき、この噺の結末につながっていく。南町奉行大岡裁きの、名裁きの典型例のような噺です。
2.神田の三河町
三河町は現在の千代田区内神田1丁目と神田美土代町。ここに家主の”多呂兵衛”と借家人の”八公”が住んでいた。同町に質屋”徳力屋”が有って、話の発端となる。
徳力屋は現在神田鍛冶町2丁目(三河町とは隣町)に本社がある”徳力”だと言われています。貴金属では日本有数の実力を持っています。私ごとで恐縮ですが婚約指輪や結婚指輪はここで作っています(関係ないか)。
過日、ある評論家(新聞記者?)が、この徳力の社長と話をしていたら、「落語の中にうちの社が出てくる噺があるそうだが、なんて言う噺か知っていますか」と聞かれたことがあったそうです。噺は知っていたが、内容が悪者になっているので言い出せず「知りません」と答えたと言うことを、話していました。なるほどと思わせるエピソードです。
| |
1727年(亨保12年)は、それ以前から徳力を冠した屋号で両替商を営んできた当主が、徳川幕府の命を受けて、新たに金銀の改鋳事業を創業した年であり、当社にとって記念すべき年です。これをさかのぼる草創期から300年、伝統と信用の当社は今日まで営々と継承され、貴金属総合メーカーとして確固たる基盤を構築してまいりました。
1900年(明治33年)初期は、それまでの200年余の歴史と経験を礎として、貴金属板、線の製造、宝飾、工芸品の加工などを開始し、その改良発展に努めた時期であり、次代への基礎技術の蓄積をはかったときでした。
1930年(昭和初頭)、時代にさきがけて、貴金属工業用材料の製造を開始。1934年(昭和9年)株式会社に改組し、わが国初の金電解精錬を工業化、また、白金ロジウム熱電対その他の製造技術を開発するなど、幾多の実績をあげました。
エレクトロニクスの進展とともに情報化時代といわれる昨今、1995年、地下に公共変電所をもつ本社インテリジェント・オフィスビルを新築し、神田駅東口周辺地域の発展と経済拠点の再構築をはかるとともに、着々と情報化装備を進め、世の中の技術革新に呼応して先端技術を磨き、生産体制を拡充し、電子産業をはじめとする各種工業用貴金属製品から歯科材料・地金・宝飾品までのあらゆる貴金属ニーズにお応えしております。 |
(株)徳力本店ホームページより http://www.tokuriki-kanda.co.jp/
3.江戸時代の通貨制度
江戸時代には「金」「銀」「銭」の3種類の通貨が併用され、それぞれの単位も異なっていました。高額貨幣として、江戸ではおもに金が使われ、大阪では銀。そのため、両替商が活躍しました。幕府が定めた公定相場(18世紀初頭)では、金1両・銀50匁・銭4000文が同じ価値。実際の相場は日毎に変動し
(変動相場制)、時代とともに銭の価値は下がりました。
「東国の金遣い、西国の銀遣い」は江戸時代の貨幣制度の特徴を端的に表した言葉です。当時、東日本では金貨建て・金貨支払い、一方、西日本では銀貨建て・銀貨支払いが普通でした。これは東日本には金の産地
(佐渡金山など)が多かったのに対して、西日本には銀の産地(石見銀山など)が多く、さらには中国との貿易で銀貨を使用した慣行があったことによるもので
しょう。
レート
寛永13年(1636)「寛永通宝」が 多量に鋳造され、銅貨の代表例として扱われ、これで金、銀、銅
(銭)の三貨が出揃い、我が国最初の貨幣制度が確立した。江戸では通常、銀貨は使われず金貨と銭が使われた。銀貨は<秤量貨幣>で、重量で使われた。
当時の公定相場は金1両=銭4貫 (4000文)=銀50匁。
幕末には 金1両=銭10貫(10000文)=銀60匁。
単位
<計数貨幣>
一両(小判)=四分=十六朱=一文銭(4,000枚)<4貫文>
一分=四朱=一文銭(1,000枚)<1貫文>
一朱=一文銭(250枚)
見れば分かるとおり、四進法になっています。
一朱4枚で一分。一分4枚で一両となっています。
一朱、一分については、金と銀のどちらかをあてはめれば良いのです。
余談;10両盗むと首が飛ぶ時代、その時の泥棒はどうするか?「九両三分二朱」盗んで、首の飛ぶのを免れた。二朱=1/8両だけ値引き(?)した。今買い物で、千円のところ「980円」と表示されると、ものすごく安く感じるのと、同じ数字のトリックか。
<秤量貨幣>銀
一両(小判)=丁銀・豆板銀(重さは50〜60匁)=五匁銀(12枚)
銀貨は大きさや品格ではなく重さ(銀の実質含有量)で価値をみた。また変動相場制のため、かならずしも50匁や60匁で交換されていたわけでは無く、相場で決まった。関西圏で
「貴金属としての価値」を重視して扱ったため実生活では使いにくく、銭または金貨が使われた。江戸後期では銀は金の下に従属し、重さではなく枚数で金と交換されるということになります。
大判について
大判は贈答用などに使われ、日常流通することはほとんどないため、大量に流通させる必要のある小判を幕府は造りました。
大判は制作者名および花押が墨書されていましたが、頻繁に流通する小判にあっては、墨書は抹消されやすいので、慶長五年(1600)年以降「一両」などの金額、花押などの文字はすべて「刻印」となり、大量生産、大量流通に適したものとなりました。
寛永通宝
寛永銭は、江戸の庶民に最もなじみの深いお金。表に「寛永通寶」の文字が入り、裏の模様は青海波。1文銭と、形が少し大きい4文銭がありました。まん中に穴があるので、紐
(ひも=さし)を通して結んでおけます。数えたお金が欠けることもないし、携帯に便利。
4.江戸の物価・東京の物価
| |
江戸:文化文政年間(1806〜1830) |
東京:2000年現在 |
| 焼き豆腐 |
5文 |
170円 |
| こんにゃく |
8文 |
200円 |
| 桜餅 |
4文 |
100〜160円 |
| 汁粉 |
16文 |
500円 |
| 鰻丼 |
100文 |
1000円 |
| かけ蕎麦 |
16文 |
550円 |
| あんま |
64文 |
|
| 風呂 |
10文 |
400円 |
| 串刺しおでん・天ぷら・イカ焼きなど |
4文 |
|
| 芝エビのてんぷら蕎麦 |
32文 嘉永六年(1853) |
1000円 てんぷら蕎麦 |
| 上等の酒1合 |
40文 嘉永六年(1853) |
450〜800円 清酒徳利1本 |
| 米 1石(=150kg) |
1両 (267文・10kg) |
7000円コシヒカリ10kg |
舞台の神田を歩く
徳力本店を探しに、JR神田駅東口を出る。北に向かって1分も歩くと、右側に宝飾品部の入った本店がある。小さなビルで上層階には関係ない別会社が入っているので、なんだこんなに小さい会社か?と思うのは早合点。裏には大きなビルがそびえている。そのビルが建つ以前は大きな木が立ち、根方には池があり魚が泳いでいた。回り近所から見たら、小さなオアシスの様な雰囲気になっていたが、都会の一
等地。止む終えず今の大きなビルに生まれ変わった。今でも秋になると落ち葉がすごかったと、近隣の人々から懐かしがられるとのことです。宝飾品部の店舗ではクリスマスセールと名を売って、金やダイヤの宝飾品を販売しています。貴金属店独特の品の良さと、私には敷居の高さがあります。しかし、出された緑茶は流石吟味されたものでした。
現在の徳力はJRの東側、神田鍛冶町2丁目。隣町が落語「紺屋高尾」の舞台になった久蔵さんが住んでいた紺屋町です。噺の中の徳力屋は西側の三河町、今の千代田区内神田1丁目と神田美土代町あたり。JRから4〜500m辺りの町です。今、ここには徳力屋さんの跡はなにも無いし、ビジネス街の中心地です。株式上場された企業のビルがいろいろ見られます。どこまで行ってもダークスーツのビジネスマンやOLが携帯電話を駆使しながら歩いています。落語の世界はどこにもありません。
 地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。
それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。
 |
江戸の通貨
大判・小判、1分金・1朱金、銀貨・寛永通宝等が有ります
|
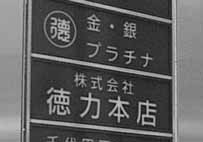 |
徳力本店ビル (千代田区鍛冶町2−9−12)
神田徳力ビルの看板と本社ビル。
「紺屋高尾」の舞台、紺屋町が隣町とは知りませんでした。
|
 |
徳力本店宝飾品部(千代田区鍛冶町2−9、=神田駅前)
ニューヨークのティファニーは言い過ぎかもしれないが、神田版ティファニーか?
|
 |
舞台の三河町(千代田区内神田1丁目と神田美土代町)が有ったところですが、大きなビルに広い道。現代ビジネス街の最先端地です。
江戸の名残は全くありません。
|
2001年12月記
次のページへ 落語のホームページへ戻る
|